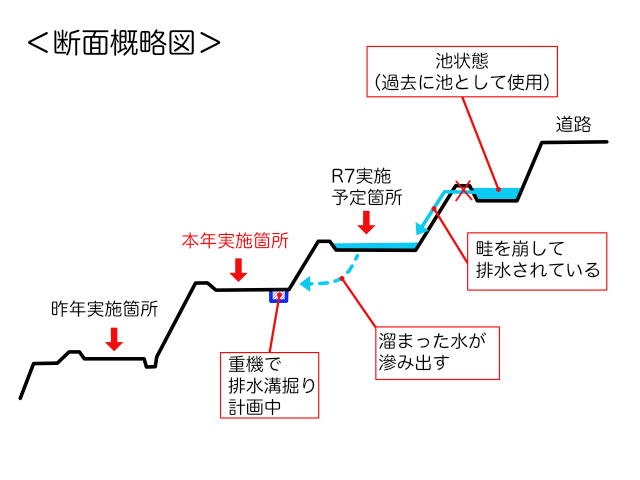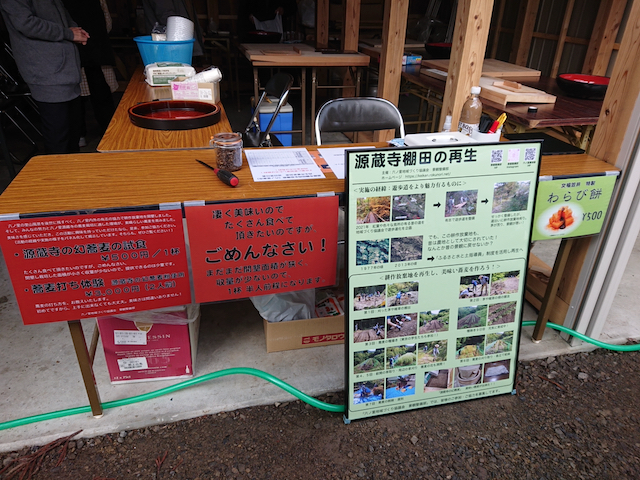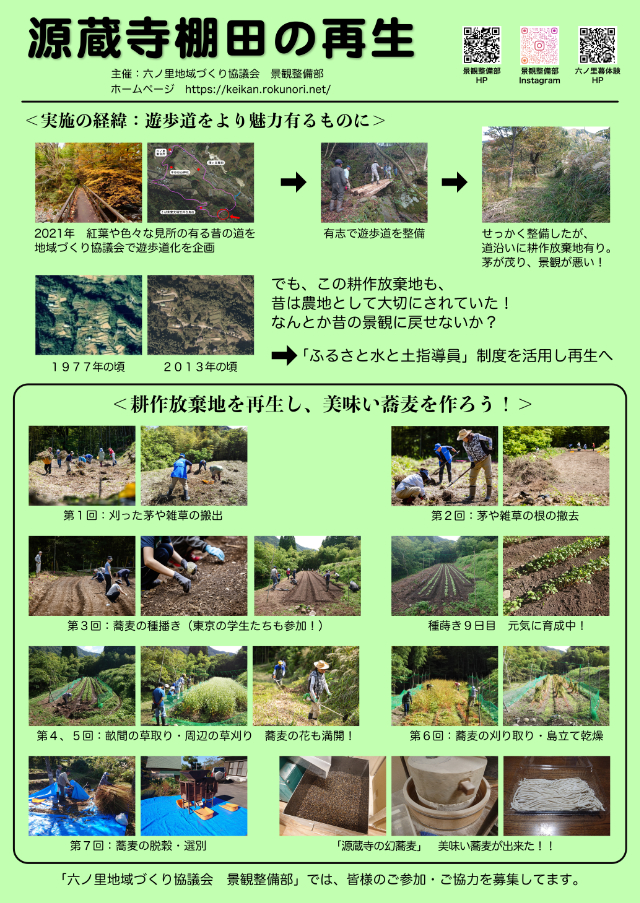ご案内していました「源蔵寺棚田の再生 第4回目」を実施しました。
東海地方も梅雨明けして暑い日が続いており、実施日当日も例年以上の暑い日でしたが、細かく休憩を取りつつ無事に作業を行う事が出来ました。
今回の参加者は、町からの一般のご協力者の方が4名、東京の自由学園の方々が21名、岐阜の東海学院大学の方々が15名、東海農政局の方々が7名、「六ノ里」の方が5名、合計56名と多くの方に参加協力いただけました。
参加いただいた皆様、誠に有り難うございました。
当日の様子を紹介する前に、事前準備の様子を紹介しておきます。

第3回目で茅の根、雑草の根の圃場外への除去を行いましたが、終わりませんでした。
翌日からスタッフと六ノ里の有志により、水草系雑草の根の処理を行なって来ました。

写真の様に水草系雑草の根が作土を多く含んでいるので、このまま圃場の外に搬出すると大事な作土を捨ててしまう事になりますので、それは出来ません。

そこで根気よく根を掘り起こして、作土と根を分けていきます。
すると写真の様に水草系雑草の根がいっぱい出て来ました。

これを1週間半ほど行い、この様に畝立て前のトラクター耕起まで何とか漕ぎ着けましたが、第4回目の数日前より雷雨が続いて、非常に残念で悔しいのですが、開催日までに畝立ての準備が出来ませんでした。

畝が出来て無いと種蒔きが出来ません。
しかし自由学園の生徒さん達には「蕎麦の種蒔き実習」を行なってもらいますので、出来ないでは困ります。
そこで保険として昨年行った圃場に畝立てを行ってますので、今年の実習はこちらで行ってもらう事にしました。
では、ここから当日の様子を紹介していきたいと思います。
 写真提供:松川哲也氏
写真提供:松川哲也氏
いつもの様に、六ノ里集会所に集合です。
今回は多くの方に参加協力いただいたので、全員が写真に写っていません。
自由学園の皆さんは「源蔵寺・畑ヶ谷遊歩道」を歩いて現地集合なので、その旨を主催者からお話しさせていただき、早速現地に向かいます。
 写真提供:松川哲也氏
写真提供:松川哲也氏
現地に着いて道具類を下ろして準備していると、程なく自由学園の皆さんが到着されました。
 写真提供:松川哲也氏
写真提供:松川哲也氏
全員が揃ったところで「ふるさと指導員」から本日の作業の概要を説明し、自由学園、東海学院大学、東海農政局、各々簡単に紹介をしていただきました。
その後、種蒔き班(自由学園の方々)と支柱作り班(東海学院大学と東海農政局の方々)に別れていただきました。
一般の参加協力の方々は常連の皆さんでしたので、今回はスタッフの補助をしていただきました。
 写真提供:松川哲也氏
写真提供:松川哲也氏
この日、畝立て用にトラクターでの耕起を六ノ里棚田米生産組合の方に行っていただいてましたので、その様子も参加者の方に説明し見学していただきました。
では、実際の作業の様子を紹介してまいります。
まずは蕎麦の種蒔き班の様子から。
 写真提供:松川哲也氏
写真提供:松川哲也氏
今年も「スジ蒔き」で行います。
4人1グループに分かれて、作業していただきます。
まず、スタッフが実際に種蒔きの仕方をやって見せて、作業の仕方や注意点を覚えていただきます。
具体的な作業方法は、まずイボ竹(農業用の支柱 直径16mm、長さ120cm)を畝の上に押し付けて、種を蒔く溝を作ります。
次に、出来た溝に紙コップに入れた蕎麦の実をつまんで入れていきます。
その後は土を掛けていくのですが、今年はここまで出来たらスタッフに確認してもらう様にしています。
と言うのは、昨年「撒く量」が分かりにくかった様子だったので、スタッフが確認する事で適量が撒かれる様にしました。
*多いと発芽した後に間引きが必要ですし、少ないと発芽しなかった所が出来ます。

説明が終わったら、グループごとに分かれて作業していただきました。
その際スタッフは各グループを見て回り、質問に答えたりアドバイスしたりしました。
 写真提供:松川哲也氏
写真提供:松川哲也氏
イボ竹を押し付けて出来た溝に、蕎麦の実を蒔く様子です。
一通り蒔けたらスタッフが蒔き具合を確認し、土の掛け方を行って見せて、参加協力の方々に実際に行ってもらいました。
 写真提供:松川哲也氏
写真提供:松川哲也氏
生徒さんだけで無く、先生がたも一緒に蒔いてくださいました。
生徒さん達と先生が一緒に作業に取り組む姿、本当に素晴らしいと思えます。
ここからは鹿避け網の支柱作り班の様子です。

今年は、ここの竹を使って作ります。
ここも元々は田んぼだったのですが、竹が侵食して来てます。
このままでは竹林になってしまいますので、その処置も兼ねて、です。
まずどの様に作るのかを「ふるさと指導員」から説明し、指導する方を紹介して実際に作業に入りました。
 写真提供:松川哲也氏
写真提供:松川哲也氏
伐採するのは危険が伴います。
特に竹は弾力が強く、伐採後に跳ね上がる危険性が高いので、経験ある指導者の方に切っていただきました。
 写真提供:松川哲也氏
写真提供:松川哲也氏
伐採された竹は、適度な太さの所で支柱の長さに切ってから、竹の枝を払って(取り除いて)いきました。
払った枝は、手の空いた方に指定場所に運んでもらいました。
この様な里山の生活で行われる作業のノウハウは、六ノ里のお父さん方が多くお持ちです。
トラクター耕起を終えた棚田米生産組合の方が飛び入りで、取り扱いを間違うと怪我をするナタやノコギリを使わず、切った竹を使う「枝の払い方」を指導してくださいました。
 写真提供:松川哲也氏
写真提供:松川哲也氏
支柱は22本作成する予定でしたが、どんどん竹が侵食して来ているので、邪魔な竹も切っていただきました。
また、遊歩道に枝が侵食して来ている邪魔な自然生えの胡桃の木も切っていただき、その片付けも参加協力いただいた方に手伝っていただきました。
それから今年の圃場に関して、重要な作業をお願いしていました。

それは圃場周辺の草刈りです。
種蒔きして鹿避け網を張りますと、なかなか草刈りが大変なところもあります。
本来なら常連の参加協力者の中で草刈機を使える方数人で行う作業ですが、今回は生徒や学生さんの数が多く、そちらへの対応で人手が裂けません。
そこで、申し訳ありませんが、常連の「草刈りのスペシャリスト」とも言える方お一人で対応願いました。
単独作業にも関わらず、完璧にこなしてくださいました。

種蒔きが終わり、鹿避け網の支柱を取付終えたところ。
ここで本日の作業は終了です。
暑い中、多くの方に参加協力いただき、本来の場所ではありませんが種蒔き、鹿避け網の支柱作りと設置を行う事が出来ました。
作業後は、それぞれに歓談しながら片付けをして解散となりました。
いつもなら集合写真を撮るのですが、諸事情により撮り逃してしまいました。
数日すると芽が出て来ます。
その様子はインスタグラムで紹介していきたいと思います。
以上、第4回目の実施報告でした。
次回、第5回目は8月17日(予備日19日)に、畝間の草取り・周辺の草刈りを行なう予定です。
またこちらのサイトでお手伝いの募集案内を行いますので、協力のご連絡をお待ちしてます!
<本計画は「岐阜県ふるさと水と土指導員」のもと、六ノ里地域づくり協議会 景観整備部と町からの協力者とで行われます。>
<追記>
翌日以降のスタッフによる作業の様子を追記してまいります。
◯ 実施日の午後

せっかく種蒔きをした所を、ニホンジカやカモシカが侵入して荒らされると困りますので、鹿避け網を設置しました。
昨年は、この作業まで自由学園の方々に手伝っていただきましたが、冒頭に書きました様に、急遽昨年実施の圃場で種蒔きを行いましたので、鹿避け網は昨年使用した物になります。
巻いてしまっておいたので、伸ばす際に絡まったりして新品の様には簡単には張れません。
なので、有志の方に手伝っていただきスタッフで張りました。
◯7月28日:開催日翌日

昨日、畝立て用のトラクター耕起をしていただいたので、畝立てを行いました。
今年の圃場は中央部分が膨らんだ異形なので、ピンクのテープ(鹿避け用のテープ)でガイド線を作りました。

それに沿って、畝立て専用機で畝を立てていきます。

トラクター耕起を行ってますが心土(作土の下の層)との境に大きな石が隠れていて、それに畝立て専用機が引っかかって真っ直ぐには出来ません。
また場所によっては作土が少なく、完全な畝になりません。

そこで機械による畝立て後に、レーキ(トンボ)を用いて畝の修正を行います。
この作業も有志の方に手伝っていただき、無事に畝立てが完了しました。
◯7月29日
天気が良く地面の温度が高いので、今年テスト的に夏蕎麦を栽培していた「そば茶寮文福笠井さん下」に耕起→畝立て→秋蕎麦の種蒔きを行い、地温が下がった夕方からの実施です。
夕方まで種蒔きを行いますので、鹿避け網の設置は明日になりましたが、朝、圃場の確認をして鹿などの侵入の痕跡が無かったので大丈夫だと思います。

昨日作った畝に、種蒔き機を使って種蒔きを行いました。

種蒔き機は割と真っ直ぐに蒔いて行けるのですが、昨日立てた畝が曲がってますので、畝上から逸脱しない様に神経を使いました。

少し深めに蒔いてますので、多分、4〜6日後には芽が出ると思います。
◯7月31日
本日、今年の圃場に鹿避け網を設置しました。

午前中に鹿避け網用の支柱を設置。

午後から鹿避け網を設置。
27日にみんなで種蒔きした圃場は、

昨日より、チラホラ芽が出て来てます!(種蒔き3日目)

そして、これが今日の様子。
出て来た芽は蕎麦殻をかぶっているので、それを種だと思って鳩やカラスが啄みに来ます。
ですので、明日、不織布を掛けます。
◯8月1日

鳥対策の不織布を掛けました。

不織布の下では、双葉が出て来ています。
全体が大体出揃ったら、不織布は撤去ですが、その前にウサギ対策で目の細かい獣害対策網を鹿避け網の下部に前週にわたって設置します。

7月29日に蒔いた今年の圃場では、8月2日、種蒔き後4日目に一斉に芽が出て来てます。
こちらの圃場は機械で深めに蒔いたので、夏蕎麦の経験上、芽が出る際に蕎麦殻が落ちて出て来るので、鳥対策の不織布は不要と思っていますが、場合によっては設置するかもしれません。
以上で、第4回目以降の様子をお伝えするのは終了といたします。
この後は、別ページにて第5回目のご案内をしてまいります。
皆様のご協力をお待ちしております。